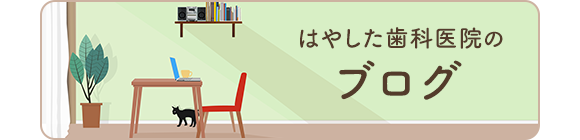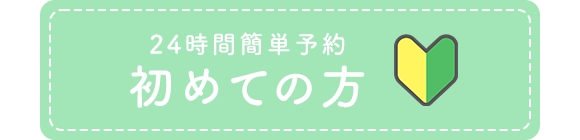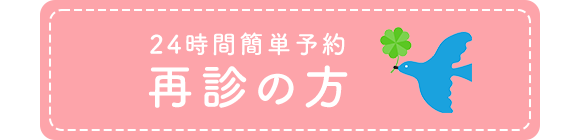Dr.トミーのビッグスマイル諫早 2023
2023年 9月
咀嚼筋のサルコペニアについて
年齢に従い筋肉の減少することを専門用語でサルコペニアと言います。
咀嚼機能とは歯で食べ物を?み砕き、舌と口蓋で食べ物を挟んで押し潰し、舌によって歯の列の上に食べ物を送ることを言います。
これらの動きが上手くできていなければ、食塊を嚥下することができなくなります。
そうなると嚥下が困難になり誤嚥性肺炎が起こります。
誤嚥性肺炎が起きないように咀嚼筋の衰えを抑制することがとても大切です。
妊娠中の患者様の抜歯の際にどう注意するか
妊娠中に抜歯をする際には安定期であれば可能です。
抜歯する際はモニター(血圧計、酸素飽和度、心電図など)を付けて行います。
歯科での座り方によっても血圧が変わることもあります。
母子の安全が優先で、妊娠の初期や後期は抜歯は緊急性がなければ避けるのが安全です。
妊婦の体位や処置時間も大切です。
チェアに妊婦さんを寝かしたまま抜歯するのは、子宮の圧迫に繋がります。
妊娠中の患者様の抜歯の際の配慮について
現在のレントゲン撮影はデジタル化しており、線量は低線量なんです。
昔と比べて線量は減っているので、妊婦さんや胎児は安心してください。
歯科医師や歯科衛生士は妊婦の精神的不安を考慮して検査の説明を十分に行う必要があります。
抜歯後の痛み止めですが、妊婦の方だけでなく胎児の動脈管の収縮にも影響があります。歯科医院ではカルナールを使っています。
手術、難抜歯に関してダメな病気について
歯周外科、難抜歯、水平に埋まっている親知らずの抜歯を行うときは注意が必要です。
全身疾患の影響によって禁忌される場合があります。
心筋梗塞の発症の場合、発症後6カ月以内の抜歯はできません。
ですから定期的に歯科医院に行くことが大切です。
2023年 8月
歯周病菌が起こす腸内細菌叢の乱れについて
歯周病というのは慢性炎症性疾患と言って痛みがなく進行します。
歯周病は心血管疾患、2型糖尿病、関節リウマチ、アルツハイマー型認知症、癌への影響などが研究結果から報告されています。
口腔内細菌というのは胃酸で破壊されると言われており腸内に届かないと考えられていましたが、最近の研究で歯周病菌が腸内まで行くことが分かりました。腸内の細菌と手をつないで増加しています。
お口の中のケアはとても大切です。
歯周病菌が起こす腸内細菌叢を介した病態への悪影響について パート1
腸内細菌叢を介して全身疾患に悪影響を与えることについてお話していきます。
1型糖尿病で歯周炎の患者さんは血中のグルコース濃度が高くなって、小腸や脾臓において炎症を誘発するような細胞を増加させたりします。
2型糖尿病はPG菌が空腹時の血糖値を上昇させます。
糖に対して異常を起こしやすいのでインシュリンを抑制してしまい、血糖値を上がってしまうということを起こしてしまいます。
歯周病菌が起こす腸内細菌叢を介した病態への悪影響について パート2
歯が痛くなった時だけ歯医者に行くという方も多いと思います。
歯周病菌というのは慢性疾患にあるために、いきなり急性を起こすと重症化するということを理解していただきたいです。
歯周病菌のPG菌が動脈硬化を起こしてしまいやすいんです。
肥満の方の場合、油ものが好きな方も多く動脈内でアテローム性動脈硬化を起こしやすく、さらに歯周病菌が増えるといずれ血管が破裂してしまうこともあります。
定期的に歯科医院に通って検診していただきたいと思います。
腸内細菌叢のバランスが乱れる状態について
腸内細菌叢とは腸内細菌の集まりです。
腸内細菌叢のバランスが乱れを専門用語でディスバイオーシスと言います。
肥満の方は、ディスバイオーシスと腸管バリア機能の低下を起こしてしまうことがあります。その結果全身的に軽微な炎症性を誘発します。
この炎症が歯周組織の破壊に繋がる可能性があります。
歯周病菌は腸管まで行って、また口腔内に戻ってきます。
腸内細菌層の乱れが歯周病菌を悪化させます。
肥満の方の場合、高脂肪食を接種しているのでお口の中の歯槽骨が重症化して歯が抜けやすい状況になりやすいです。
食品で細菌叢を整えるプロバイオティクスについて
食べることで善玉菌を増やすことについて話をします。
お口の中には700種類以上の細菌があります。
口腔内の細菌叢のバランスを整える食品の摂取により歯周病の予防をして、有益な菌を残すことについて話をしていきます。
抗生物質を使い過ぎていると、抗菌薬が効かなくなって耐性菌が増えます。
有益な菌を残す乳酸菌の一種にロイテリ菌というものがあります。
これが歯周病菌を抑制する働きが確認されています。
2023年 7月
歯列の成長と食べているものを把握していきしましょう パート2
離乳食が始まった頃、歯はあまり機能していません。
離乳食は舌で潰せるぐらいの硬さになります。
乳臼歯が萌出する時期は歯茎で食べる時期になります。
離乳食の後期で離乳食は歯茎で潰せるぐらいの硬さになります。
ここで注意しておきたいのが、歯の萌出が遅いと月齢が離乳食後期であっても、歯茎で潰せない可能性があります。
月齢ではなく口の中状況を確認することが大切です。
歯で食べられるようになる時期 パート1
第一乳臼歯といって前から数えて4番目の萌出が完了すると歯で食べる時期になってきます。
乳歯は20本生えます。
歯で噛み潰せる硬さの食事ができるようになります。
第一乳臼歯の咬合ができていないと、上手く食べることができません。
第二乳臼歯が萌出完了すると、ほぼ硬さとしては普通の食事ができるようになります。
歯で食べられるようになる時期 パート2
今回は、乳歯が永久歯への交換時期に起こることをお伝えしていきます。
乳歯から永久歯に代わるのは、奥歯より先に前歯です。
前歯が抜けている時、噛み切れないことがあります。
正常に交換が進めば問題ありませんが、何らかの問題があって永久歯が出てくる時期が遅くなって、噛み切る動作が必要な大きさの食べ物にしなくてはいけなくなります。
乳幼児の成長時期(生後5カ月から6カ月)について
生後5カ月から6カ月は離乳食初期でごっくん期とも言われます。
リンゴをスライスして食べさせたら詰まって意識不明になってしまったとか、卵アレルギーがあるのに卵を食べさせてしまった、ということもあります。
この時期は専門的に嚥下機能獲得時期と言います。
ポタージュ状、ヨーグルト状のものを食べられるようになります。
しかし、粒が混在していて均一滑らかでないと飲み込めません。
離乳食を始める4つの条件があります。
(1) 首がすわって、寝返りができる
(2) ささえながら5秒以上座ることができる
(3) 食器を舌で押さえることができる
(4) 食べ物に興味がもてる
2023年 6月
小児期に大切な口の周りの筋肉の働き
顔面の皮膚の内部に表情筋という筋肉があります。
これによって人は様々な表情を作って感情を表現することができます。
表情筋の一つに唇の周りに口輪筋というものがあります。
この筋肉は口の中に食べ物を入れて口を閉じる力があります。
表情筋は成長期における歯並びに常に負荷をかけます。
頬の力によって歯並びにも影響があります。
食事中、口を閉じて食べ物を食べる習慣が大切です。
小児期に大切な舌の構造と機能について
解剖学的に見ると、舌は様々な方向に筋肉があり、脂肪がなく複雑な動きができます。
筋肉があるために摂食嚥下や食塊形成などの役割が舌にはあります。
しかし、成長期に舌が上あごに付かないと正しく嚥下できません。
舌の筋肉を獲得することはとても大切です。
口腔機能の発育に影響を与えます。
食べ物が咀嚼によって砕かれ、唾液と混和して食べ物の塊を作ります。
舌の力が弱いと食べ物の塊うまくできずに、食べ物が食道に誘導されません。
食べる機能の中で大切な咀嚼について
歯科において咀嚼というのは?み合わせ、口腔機能、心理の3つで成り立つと考えられています。
口腔機能において、子供は嫌いなものだと飲み込めないことがあります。
自宅だと良く噛んで食べることができるのに、学校では最近は給食時間が短くなっていて、あまり噛まずに食べてしまっていることもあります。心理的な要因にも関わってきます。
食事に関してストレスを感じながら食べていることもあります。
歯列の成長と食べているものを把握していきしましょう パート1
歯列とは歯並びのことです。
食べる機能の発達は歯並びと密接な関係があります。
小児の場合、多くの乳歯が脱落して前歯で噛み切れない、臼歯で噛み締められないような時期もあります。
3歳ごろに乳歯の歯並びは完成します。
6歳ごろに永久歯の萌出があり、12歳ごろまでに歯列が完成します。
ところが、中学生でもまだ乳歯が残っていることもあります。
早めに乳歯を取らないと、永久歯の萌出位置が歯並びから外れてしまうことがあります。
12歳から13歳ごろに第2大臼歯が出てきて、これが出てきて?み合わせが安定するのに1,2年かかるので14歳から15歳で安定しますので、把握しておいてください。
2023年 5月
介護施設で利用する湯呑の使い方 パート2
飲み口が小さい高齢者の方の様子を想像してみてください。
大きい飲み口と小さい飲み口ではどちらの湯呑が高齢者の方にとって飲みやすいでしょうか。
大きい飲み口の方が飲みやすいです。
介護施設の入居者の方が正しい姿勢を取ることも大切です。
テーブルが高過ぎるたり、前かがみであったり、後ろを向きすぎると、咽頭運動を抑制しているため誤嚥する可能性が高まります。
口腔癌に気づいてほしい パート1
口腔癌の診断は難しいです。
もし歯科医院で口内炎と間違えて、レーザーを当てて悪化してから病気が気づくこともあるかもしれません。
歯茎に現れる病変として3つあります。
(1) 早期の癌で表面に指を触れると簡単に出血したり、表面が赤くなっている
(2) 表面がカリフラワー状でぐじゅぐじゅしている
(3) 歯茎にしこりがあって、触ってみて少し硬い
これらの症状があった場合は歯科医院で早めに診てもらってください。
口腔癌に気づいてほしい パート2
歯肉の病用についてさらにお話いたします。
歯茎がざらざらしていたり、痛みは無いが歯科医院に行かずに2か月程度経ったときに、粘膜の下の組織が赤みを帯びて癌の段階がエスカレートしてしまうことがあります。
歯茎に乳頭状の白いところと赤いところが混在していたり、少し盛り上がった状態というのは癌の状況です。
親知らずを抜歯した後に、歯肉癌が発見されることもあります。
誤解していただきたくないのは抜歯したから癌になったということではありません。
そのところに癌の細胞がたくさんあったということです。
抜歯の前に歯科医師から歯茎の状況の説明をしてもらってください。
口腔癌に気づいてほしい パート3
今回は口蓋の癌についてお話します。
口蓋には口蓋腺といって唾液を出すところがあり、こういったところがジュクジュクした状態になって、口内炎の軟膏を塗っても治らないという場合があります。
歯科医院で口内炎と間違えてレーザーを使用した場合には、組織が悪化するので注意が必要です。
癌細胞が歯と骨の間の歯根膜に入り込んで顎の中まで入り込むことがあります。
そういった際は顎の骨まで削らないといけないケースがあります。
早期発見、早期治療のため歯科医院に行って診てもらってください。
口腔癌の現状について
今回はこれまで私がなぜ口腔癌についてお話してきたか、ということについてお話します。
日本での癌の罹患率は癌の中で約2%です。
しかし罹患すると食事は食べれない、飲み物も飲めない、話もできない、呼吸も難しくなります。
生活の質が著しく低下してしまいます。
2016年に口腔咽頭癌の患者さんは2万人を超えました。
日本は超高齢化社会が進み、免疫力が低い人が増えるため、癌患者は増えていきます。
2015年に死亡率は50%を切って37.9%であり、なかなか減少していません。
アメリカでは1995年の25.8%から2015年の18.9%に減少しています。
アメリカやイギリスなどの先進諸国では、早期発見、早期治療に国がバックアップしています。
日本では口腔癌検査をどこで行うか決まっていません。
当院では口腔癌が発生しないかどうか、口腔メンテンナンスを行いながら歯科衛生士も理解して早期発見をしています。
皆さんも日本の歯科の現状を知っておいてください。
2023年 4月
睡眠時無呼吸に起こる症状について
睡眠時呼吸ができないことで起こる3つの症状があります。
(1) いびき
(2) 起床時に頭が痛い
(3) 日中の過度な眠気
他にも熟睡感の欠如、倦怠感、夜の頻尿、集中力の低下などがあります。
この症状が起こってしまうメカニズムについてお話したいと思います。
肥満の方は起こりやすいです。首や喉の周りの脂肪や顎が小さい、鼻炎、扁桃腺が多きなどによって、軌道が閉塞して呼吸がしにくくなります。
摂食嚥下障害における介護施設での対応について パート1
摂食嚥下障害についてお話します。
外来において、高齢者の方に多く起こっていることを感じます。
介護施設においては嚥下障害を起こす割合は45%、特養においては60%が確認されています。
ほぼ2人に1人は摂食嚥下障害の可能性があります。
摂食嚥下障害と器質的障害、機能的障害、加齢による影響の3つが重なってしまうことがあります。
摂食嚥下障害における介護施設での対応について パート2
要介護者の摂食嚥下障害というのは3つ重なっています。
器質的障害、機能的障害、加齢による影響、こういう障害が重なって介護が難しくなっています。
義歯が不適合の場合、外来と違って訪問した場合には入れ歯が合わなくなる可能性があります。原因は筋肉の硬直、粘膜の浮腫などがあります。
浮腫みの理由として要介護者の場合は薬剤の服用、水分の過剰摂取、運動不足などがあります。
口の中で上顎の粘膜が浮腫みやすいです。
上顎の内側には大きな動脈が通っていて浮腫みやすいです。
介護施設で利用する湯呑の使い方 パート1
ご高齢者の方が利用する湯呑によって誤嚥リスクがあることをお話します。
頭が後ろ向きになると、首が伸びきって咽頭の運動を抑制し、誤嚥のリスクが高まります。
飲み物の量が減ってきて湯呑を傾けた時、鼻に当たらずに飲めれば自然な形で飲むことができます。
小さなマグカップと大きなマグカップでは、鼻に当たらないのは大きなマグカップです。
傾けた時に鼻に当たらないような大きさの湯呑を選んでください。
もし湯呑の飲み口が小さい場合はどうなるんでしょう?次回お話いたします。
2023年 3月
コロナ感染の予防を家庭でどうやって行うか パート3
鼻うがいで鼻の通りが悪いのも解消されます。
新型コロナウィルス対策としても有効です。
生理食塩水を容器に入れて少し前かがみになります。
片方の鼻の穴から流し込んで反対の鼻の穴から出します。
外から持ち込んでしまったウィルスを家庭に持ち込まない効果があります。
口腔機能低下の社会的背景について パート1
65歳以上の単身世帯の高齢者の方々が会話をする機会というのが減っています。
会話が2,3日に1回程度の方も多いです。
2週間に1回以下の男性が16%以上もいるという報告もあります。
お口の機能が低下することをオーラルフレールと言います。
そうすると認知機能も低下してしまいます。
口腔機能低下の社会的背景について パート2
口腔機能を維持することで全身のフレールの予防ができます。
口腔機能低下の診断があっても、具体的な対処方法が医療従事者から示されていないという課題があります。
口腔の体操(あいうべ体操)が有効です。
歌を歌うことも口腔の機能が助けれらますので知っておいてください。
口腔機能を一般的にどう維持するか
唾液は1日に1リットルから1.5リットル分泌します。
粘膜を保護したり、汚れを自浄したり、抗菌作用があったり、消化を助けたり、様々な作用があります。
65歳以上の3人に1人は唾液の分泌障害があります。
歌を歌うことによって唾液の分泌が増加することが分かっています。
また嚥下の力も上がることも分かっています。
2023年 2月
歯周病が酷くてインプラント治療するとどうなるか
適切な治療を受けていない人が、歯がなくなってインプラントを入れようと来院する場合があります。
うまくインプラントが生着しないばかりか、インプラント周囲炎を起こすことがあります。
歯がなくなる方には、虫歯でなくなる方、歯の根っこが折れてしまった方、歯周病が酷くてなくなる方がいますが、歯周病が酷い方の場合にはインプラント周囲炎で抜けてしまう場合があります。
介護施設などで刻み食が誤嚥を起こしてしまう
通常の食事で咀嚼ができなくなってしまった方に刻み食を提供する場合が多いです。
刻み食の場合は咽頭の中に流れ込んで、喉頭蓋が上手く機能せずに肺に入り込んでしまいます。
普通食を上手く食べれるようになることが望ましいです。
むせがなく刻み食が流れ込んでしまうことを不顕性誤嚥と言います。
介護施設などでどう対応して食事を行うか
入居者の方が安全な嚥下姿勢についてお話をします。
3点あります。
(1)うなずき頭位
(2)姿勢の保持
(3)足底の設置
膝よりも手前に足を置くことが大切です。
おしりより上半身が後ろに傾斜していると、腰が前方にすべって背中が丸まった姿勢になり、嚥下の運動が抑制されてしまいます。
また腹圧が上昇してしまい、横隔膜が上に持ち上げられて咳払いができずに誤嚥のリスクが高まります。
コロナ感染の予防を家庭でどうやって行うか パート1
家庭でコロナ感染予防に対してできることとしてうがいや手洗いがあります。
呼吸で体内に入る空気は1日1万リットルで、呼吸回数2万回以上です。
ほこりや細菌、ウィルスが含まれていて、鼻の奥にある上咽頭に溜まってしまいます。これはうがいや水分では届きません。
どうすればいいか、鼻うがいなんです。
歯科医院でも使用しているフローという容器を使って行います。
コロナ感染の予防を家庭でどうやって行うか パート2
鼻うがいでコロナウィルス感染についてお話をしていきます。
歯科医院ではフローというものがあります。
少量でやっていこうという方はスポイトや小さな樹脂製のボトル、醤油さしのようなものを使っていただきたいです。その中に生成水やミネラルウォーター100mlに食塩を1gを入れて生理食塩水を作ってください。5ml程度をスポイトや樹脂製のボトルに入れてください。
2023年 1月
介護施設でコロナが起こる原因について パート1
今回も認知症の分類についてお話していきます。
一番多い認知症はアルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症は女性に多く、日本の認知症の患者数は462万人のうち60%にあたる277万人いると言われています。
脳内に不要なたんぱく質が溜まってしまいアルツハイマー型認知症の原因になります。
口腔内に歯周病菌が多いと血管を通って急激にアルツハイマー型認知症が進行しますのでご注意ください。
介護施設でコロナが起こる原因について パート2
オミクロン株の前に流行したのがデルタ株でした。
このデルタ株というは咽頭で感染がしやすいものでした。
レビー小体型認知症の方の場合は嚥下機能障害があり、誤嚥性肺炎を起こしたりします。
デルタ株に感染したレビー小体型認知症の方は、食事が上手くできないことがあり、誤嚥性肺炎を起こしやすいと推測しています。
認知症の分類について パート1
前回まで認知症のうち、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症についてお話しました。
他にも分類があります。
血管性認知症についてお話します。
脳内出血とか脳梗塞を起こしてしまい脳内の神経組織が破壊されて起こる認知症が血管性認知症です。
男性に多いという報告があり、日本の認知症の患者数は462万人と推定されており、そのうち血管性認知症は20%の92万人いると言われています。
認知症の分類について パート2
今回も認知症の分類についてお話していきます。
一番多い認知症はアルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症は女性に多く、日本の認知症の患者数は462万人のうち60%にあたる277万人いると言われています。
脳内に不要なたんぱく質が溜まってしまいアルツハイマー型認知症の原因になります。
口腔内に歯周病菌が多いと血管を通って急激にアルツハイマー型認知症が進行しますのでご注意ください。